『海に沈んだ対馬丸 子どもたちの沖縄戦』
『海に沈んだ対馬丸 子どもたちの沖縄戦』
早乙女 愛・著 岩波ジュニア新書 2008年
映画「満天の星」のパンフレットで、監督の寿大聡と著者の対談が載っていた。この本の取材でインタビューした中島高男さんの映像が、映画でも使われていた。
なぜ学童疎開が行われたのかといういきさつ、乗客たちそれぞれの事情、撃沈、漂流生活、上陸後、という順に対馬丸事件がたどられていく。
そもそもなぜ疎開か。日本本土への攻撃の防波堤となる沖縄に次々兵士が送り込まれ、その食糧確保が主な目的だったという。戦場となる沖縄から安全な場所への移動という面もあっただろうが、高齢者、女性、子どもが対象だったことから、戦力外の人員整理の目的の方が大きかったように思える。
意外だったのは疎開そのものは対馬丸の前に、既に7月中旬に一般疎開者が、学童疎開の第一陣が8月14日に発っていたことだ。てっきり対馬丸が最初の疎開船だと思っていた。そして対馬丸の他に2隻の疎開船、2隻の護衛艦がいたことも。この合計5隻の船団が航行していたのだ。そのうち学童疎開船が対馬丸だった。映画でこのことも言っていたのかも知れないけど、記憶にない。
ああ、だからか、と腑に落ちた。護衛艦がなぜ対馬丸の遭難者を救助しなかったのか。映画では全滅を避ける為(ちょっと身勝手な感じがした)と言っていたが、他の2隻の船を護衛しなければならなかったからなのか。使命を果たしただけだったのか。
他の船に乗っていたランドセルだけが帰ってきた、という話が映画にありどういうことかと思っていたが、このことを知って理解できた。
著者が訪ねて話を聞いた7人の生存者たち。彼らの証言を元にした沈没から漂流生活の描写は凄まじい。映画のインタビュー画像よりももっともっと過酷だった。
救助されたのが漂流中の人もいるが、何日も漂流して無人島に上陸し、沖を通る漁船にようやく救助された人もいた。ここらへんは映画では詳しく分からなかった。漂流中に亡くなった人も多かっただろう。もっと早く救助出来なかったのかと思われてならない。
印象的だったのは救助後のこと。箝口令が引かれていたため、一緒に乗っていて助からなかった児童の家族からの問いかけに答えられず、責められてしまう。どんなに辛かったろう。そうでなくても目の前で友人が家族が沈んでいくのを見るしかなかった事実に打ちのめされていたのに。何と酷なことを子どもに強いたのだろう。
さらに沖縄に戻った後に今度は空襲に遭い家を焼かれた話もあって、いったいどこまで子どもたちの苦難は続くのか。
この取材の後亡くなった方もいる。「黒川の女たち」でも思ったが、記録して残してくれたことに感謝したい。そしてこれを読んだわたしたちができることは何なのか、考えていきたいと思う。
この本を読んだ後に、大城立裕『対馬丸』を読んだが、けっこう重複している部分があり、どちらの記載にあったのか混乱してしまった。だから正確ではないかもしれないけれど、思うことを書いてみた。『対馬丸』についてはまた別に書く。
早乙女 愛・著 岩波ジュニア新書 2008年
映画「満天の星」のパンフレットで、監督の寿大聡と著者の対談が載っていた。この本の取材でインタビューした中島高男さんの映像が、映画でも使われていた。
なぜ学童疎開が行われたのかといういきさつ、乗客たちそれぞれの事情、撃沈、漂流生活、上陸後、という順に対馬丸事件がたどられていく。
そもそもなぜ疎開か。日本本土への攻撃の防波堤となる沖縄に次々兵士が送り込まれ、その食糧確保が主な目的だったという。戦場となる沖縄から安全な場所への移動という面もあっただろうが、高齢者、女性、子どもが対象だったことから、戦力外の人員整理の目的の方が大きかったように思える。
意外だったのは疎開そのものは対馬丸の前に、既に7月中旬に一般疎開者が、学童疎開の第一陣が8月14日に発っていたことだ。てっきり対馬丸が最初の疎開船だと思っていた。そして対馬丸の他に2隻の疎開船、2隻の護衛艦がいたことも。この合計5隻の船団が航行していたのだ。そのうち学童疎開船が対馬丸だった。映画でこのことも言っていたのかも知れないけど、記憶にない。
ああ、だからか、と腑に落ちた。護衛艦がなぜ対馬丸の遭難者を救助しなかったのか。映画では全滅を避ける為(ちょっと身勝手な感じがした)と言っていたが、他の2隻の船を護衛しなければならなかったからなのか。使命を果たしただけだったのか。
他の船に乗っていたランドセルだけが帰ってきた、という話が映画にありどういうことかと思っていたが、このことを知って理解できた。
著者が訪ねて話を聞いた7人の生存者たち。彼らの証言を元にした沈没から漂流生活の描写は凄まじい。映画のインタビュー画像よりももっともっと過酷だった。
救助されたのが漂流中の人もいるが、何日も漂流して無人島に上陸し、沖を通る漁船にようやく救助された人もいた。ここらへんは映画では詳しく分からなかった。漂流中に亡くなった人も多かっただろう。もっと早く救助出来なかったのかと思われてならない。
印象的だったのは救助後のこと。箝口令が引かれていたため、一緒に乗っていて助からなかった児童の家族からの問いかけに答えられず、責められてしまう。どんなに辛かったろう。そうでなくても目の前で友人が家族が沈んでいくのを見るしかなかった事実に打ちのめされていたのに。何と酷なことを子どもに強いたのだろう。
さらに沖縄に戻った後に今度は空襲に遭い家を焼かれた話もあって、いったいどこまで子どもたちの苦難は続くのか。
この取材の後亡くなった方もいる。「黒川の女たち」でも思ったが、記録して残してくれたことに感謝したい。そしてこれを読んだわたしたちができることは何なのか、考えていきたいと思う。
この本を読んだ後に、大城立裕『対馬丸』を読んだが、けっこう重複している部分があり、どちらの記載にあったのか混乱してしまった。だから正確ではないかもしれないけれど、思うことを書いてみた。『対馬丸』についてはまた別に書く。
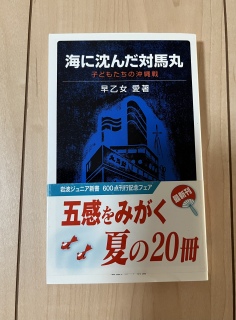
コメントを書く...
Comments