『サフラジェットの病院』
『サフラジェットの病院 第一次大戦下、女性の地位向上のための戦い』
ウェンディ・ムーア著 勝田さよ訳 みすず書房 2024年
第一次大戦下ロンドンで医師も看護師も事務員も女性だけで運営された病院があり、「ロンドン最高の病院」という評価を受けていたという。そのエンデルストリート陸軍病院 の1915年の開設から閉鎖される1920年1月までの歴史を、膨大な資料を駆使して描き出したたいへんな力作。
まずそんな病院があったなんて知らなかった。本国でも今は忘れ去られた存在であるという。そのことが「女性たちの活躍を認めたくない、世間に知らせたくない」という男性社会の姑息な悪意を感じて怒りが込み上げてくる。読みながら何度「ぐわ〜!」と叫んだかわからない。彼女たちが求めたのはただ「平等な待遇と公正な扱い」だけなのに。
1910年代に女性の医師はいるにはいたが、まともな仕事はさせてもらえず、女、子供しか診察させてもらえなかった。そもそもどんなに優秀でも医学を学ぶ道もなく、ようやく医師の資格を取ってもまともな仕事をさせてもらえない。女性は男性と結婚し家庭を守ることが役目だと世間の目は厳しい。この時代で結婚もせず30歳すぎて医師の仕事をしようなんて女性は変わり者でしかなかった。
(ナイチンゲールもそんな世間の目に苦しみ「死にたくてたまらなかった」のも無理はないという記述があり驚いた。『ゴースト&レデイ』にもフローが死にたがっているというエピソードがあったので)
それが戦争で人手が足りなくなり、さまざまな職業で女性に担い手になってもらおうという気運が高まり、女性の地位向上のチャンスが訪れた。戦争という悲惨な出来事がそのきっかけになったことには、複雑な思いがある。それとこの女性たち、医師も看護師もかなり裕福な家の子女であったことも大きい。医療隊を組織し物資を調達できる財力がないととても無理なことだった。とても恵まれた女性たちだったことも事実で、そこにも少し複雑な気持ちになるが、それでも困難な道に挑んだ女性たちは素晴らしい。
最初はフランスに渡りそこでの経験と成功を元に、ロンドンの病院を任せられる。そこで最高の評判を得、女性も男性と変わらず仕事ができることを証明できて前途は明るかったはずなのに。戦争が終わると環境は一変する。こじ開けられた扉は再び閉ざされる。女性を受け入れていた学校も医療機関も次々門戸を閉ざす。どれほど悔しかったろうか。
戦後男性医師と結婚し自分は医師を辞めた女性が、5歳の息子に戦争中医師だった思い出を話すと「看護婦だよ、医師は男性、女性は看護婦だよ」と諭されたという話には、やりきれない思いがする。あんなに優秀な医師だったのに。
時代は変わり女性の社会進出が進み、女性医師も珍しくなくなった。彼女たちが望んだことはある程度は達成されただろうけど、まだまだの部分もある。訳者あとがきにもあるように、
「だれもが特別扱いされず、1人の人間として正当に評価され尊重される、そんな世の中が実現してほしい」
作中サフラジェットについての記述もあり、『小さなことばたちの辞書』と『ウーマン・イン・バトル』を参照しながら読んだ。エンデルストリート病院を運営した2人の女性医師フローラ・マレーとルイザ・ギャレット・アンダーソンはサフラジェット運動にも傾倒していた。
1918年イギリスは21歳以上の男性と30歳以上の女性に(条件付きだが)参政権を認めた。なぜ年齢に差があるのか、それは3対2で男性票が女性票を確実に上回るようにするためだったという。なんじゃそれ!10年後の1928年ようやく女性も男性と同等の権利を得た。
ちなみに世界で1番早く女性が参政権を得たのは1893年のニュージーランド。1902年にオーストラリア。ヨーロッパで1番早かったのは1906年のフィンランド。アメリカが1920年。イギリスが結構遅かったのが意外だった。
ウェンディ・ムーア著 勝田さよ訳 みすず書房 2024年
第一次大戦下ロンドンで医師も看護師も事務員も女性だけで運営された病院があり、「ロンドン最高の病院」という評価を受けていたという。そのエンデルストリート陸軍病院 の1915年の開設から閉鎖される1920年1月までの歴史を、膨大な資料を駆使して描き出したたいへんな力作。
まずそんな病院があったなんて知らなかった。本国でも今は忘れ去られた存在であるという。そのことが「女性たちの活躍を認めたくない、世間に知らせたくない」という男性社会の姑息な悪意を感じて怒りが込み上げてくる。読みながら何度「ぐわ〜!」と叫んだかわからない。彼女たちが求めたのはただ「平等な待遇と公正な扱い」だけなのに。
1910年代に女性の医師はいるにはいたが、まともな仕事はさせてもらえず、女、子供しか診察させてもらえなかった。そもそもどんなに優秀でも医学を学ぶ道もなく、ようやく医師の資格を取ってもまともな仕事をさせてもらえない。女性は男性と結婚し家庭を守ることが役目だと世間の目は厳しい。この時代で結婚もせず30歳すぎて医師の仕事をしようなんて女性は変わり者でしかなかった。
(ナイチンゲールもそんな世間の目に苦しみ「死にたくてたまらなかった」のも無理はないという記述があり驚いた。『ゴースト&レデイ』にもフローが死にたがっているというエピソードがあったので)
それが戦争で人手が足りなくなり、さまざまな職業で女性に担い手になってもらおうという気運が高まり、女性の地位向上のチャンスが訪れた。戦争という悲惨な出来事がそのきっかけになったことには、複雑な思いがある。それとこの女性たち、医師も看護師もかなり裕福な家の子女であったことも大きい。医療隊を組織し物資を調達できる財力がないととても無理なことだった。とても恵まれた女性たちだったことも事実で、そこにも少し複雑な気持ちになるが、それでも困難な道に挑んだ女性たちは素晴らしい。
最初はフランスに渡りそこでの経験と成功を元に、ロンドンの病院を任せられる。そこで最高の評判を得、女性も男性と変わらず仕事ができることを証明できて前途は明るかったはずなのに。戦争が終わると環境は一変する。こじ開けられた扉は再び閉ざされる。女性を受け入れていた学校も医療機関も次々門戸を閉ざす。どれほど悔しかったろうか。
戦後男性医師と結婚し自分は医師を辞めた女性が、5歳の息子に戦争中医師だった思い出を話すと「看護婦だよ、医師は男性、女性は看護婦だよ」と諭されたという話には、やりきれない思いがする。あんなに優秀な医師だったのに。
時代は変わり女性の社会進出が進み、女性医師も珍しくなくなった。彼女たちが望んだことはある程度は達成されただろうけど、まだまだの部分もある。訳者あとがきにもあるように、
「だれもが特別扱いされず、1人の人間として正当に評価され尊重される、そんな世の中が実現してほしい」
作中サフラジェットについての記述もあり、『小さなことばたちの辞書』と『ウーマン・イン・バトル』を参照しながら読んだ。エンデルストリート病院を運営した2人の女性医師フローラ・マレーとルイザ・ギャレット・アンダーソンはサフラジェット運動にも傾倒していた。
1918年イギリスは21歳以上の男性と30歳以上の女性に(条件付きだが)参政権を認めた。なぜ年齢に差があるのか、それは3対2で男性票が女性票を確実に上回るようにするためだったという。なんじゃそれ!10年後の1928年ようやく女性も男性と同等の権利を得た。
ちなみに世界で1番早く女性が参政権を得たのは1893年のニュージーランド。1902年にオーストラリア。ヨーロッパで1番早かったのは1906年のフィンランド。アメリカが1920年。イギリスが結構遅かったのが意外だった。
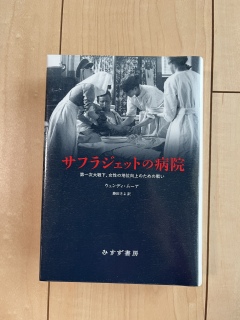
コメントを書く...
Comments