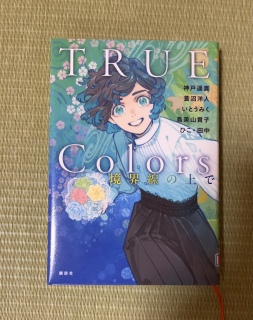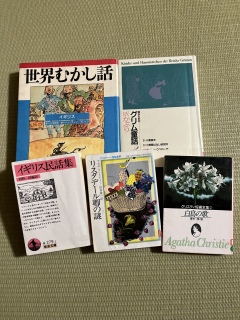昨日は明け方からまたふらつきが出た。春にもあったがあの時よりひどく、立ってるだけで体がゆれる。起き上がる時、立ち上がる時、歩く時、ふらつきが出る。それが長く続くので気持ち悪くなってきた。洗濯物干す時は上を向くのでこれも辛い。娘を起こして家事をバトンタッチして寝ることにした。寝ていても体を動かすと気持ち悪い。それでも午前中寝ていたらマシになったので、昼からは起きていた。すると今度は頭が痛くなってきた。
あれ?これもしかしたら低気圧のせいなのか?普段そんなに影響受けないのだが、たまたま今回は前日に草取り、その前日にエアコンの掃除と、首に負担かかる作業を続けてやっていたから、そのせいで影響を受けやすくなっていたのかもしれない。
とにかくこういう時は寝るのが1番。さっさと寝ればいいのに、ついフィギュアスケートの結果をライブリザルトで追ってしまった。いかんいかん。
それでもいつもより早く床についたので、今朝はだいぶ改善していた。多少ふらつくかな、という程度。やっぱり睡眠が1番の薬だ。
今日もあまり動かず基本寝ることにする。
『TRUE Colors 境界線の上で』
講談社 2025年
2023年刊行の「ジェンダーフリーアンソロジー TRUE Colors」の第2弾。
テーマは同じく「ジェンダーと中学生」 ひこ・田中と、いとうみく以外は初めての作家さん。それぞれおもしろかった。
神戸遥真『To be a Mom』
主人公が疑問を覚えた言葉「生理は将来ママになるために必要なもの」 そうかここで引っ掛かるのかと驚いた。確かに女の子は母親になるものと決めつけられている。自然とそう思わされている。わたしもそれが当たり前だと思ってきたけど、もっと自由に考えていいよね。
蒼沼洋人『三月のグラウンド』
女の子は甲子園に出られない。誰よりも努力し、体を鍛え技術を磨きエースの地位を得た主人公でも、高校野球の世界ではグラウンドに立てない。だが努力を続け、何度でも高野連に働きかけよう。それは未来につながる。いつかかなう。子どもたちにそれを信じさせてほしい。
いとうみく『親友のカレ』
自分の中に差別や偏見があることに気づくのは辛い。でもそれを自覚できたのはいいことだ。「自分のこともわからないのに、他人のことをわかったつもりになるのは傲慢だ、わかったつもりでいるより、わからなくていい」という言葉にハッとする。それでも大事な友だちのことはわかりたい、という気持ちは持ち続けていてほしい。
鳥美山貴子『ダイニングテーブル』
あーこれわかるな。どんなに家事分担を決めても、結局気づいた人の負担が大きくなる。それでも少しずつ改善されていくのが良かった。
ひこ・田中『ぼくと、体と。』
痴漢の加害者は男、被害者は女。たしかに普通そう思う。でも主人公は被害にあう。加害者になるのは嫌だけど、被害者になるのはもっと嫌だと彼は気づく。
それぞれの作品で中学生たちが真剣に悩み、気づき、前に進んでいく姿に、胸があつくなる。どうかこの子たちの未来が、より良いものでありますように。
中国大会始まった。先週のフランス大会と違って時差が1時間しかないので、リアルタイムで追っかけられる。4カテゴリー全部を1日でやるので、さくさくと進む。寝不足にもならなくてすむ。
何といってもペアのスイハンが注目。フランス大会のアイスダンスのシゼロン組は、同じ復帰でも相方が違ったけど、スイハンはそのまま。カップル競技は割と組み替えが多いけど、この二人はずっと組んでる。
日中は暖かくなるとの予報だったけど、部屋の中は20度を切ったままだった。娘が寒さから体調不良で動けなくなっているので、ついに暖房を入れた。冷房から暖房に切り替える時、エアコンの掃除をするのだが、今年はいつまでも暑かったので、なかなか掃除に踏み切れなかった。そうしてるうちにあっという間に寒くなったので、慌てて今日掃除した。ただ自分で出来ることは限りがある。前回から2年経ってるのでそろそろ業者にエアコン掃除を頼もうと思う。
足が冷えるのでスリッパも冬用に替えた。まだ使わないけど湯たんぽも出してきた。毛布と敷パットもスタンバイしている。
読書会の課題書の中に、グリムの「盗賊の花婿」が出てきて、この話がイギリスの昔話の「ミスター・フォクス」とほぼ同じ話であることを知った。さらにペローの「青ひげ」とも類似点があると。グリムと比べると「ミスター・フォックス」の方がより怖い。昔話は採集する時期、場所、語り手、そして再話する人によっていろいろ違いが出てくるのでおもしろい。
『語るためのグリム童話2』
小澤俊夫/監訳 小澤昔ばなし研究所/再話 オットー・ウベローペ/絵 小峰書店 2007年
『世界むかし話 イギリス』
三宅忠明/訳 クエンティン・ブレイク/画 ほるぷ出版 1988年
『イギリス民話集』
河野一郎/編訳 岩波文庫 1991年
「青ひげ」で思い出したのが、クリスティの短編「うぐいす荘」だ。懐かしくて再読した。「うぐいす荘」は創元版のタイトルで、早川版だと「ナイチンゲール荘」になる。わたしは最初にクリスティに出会ったのが創元推理文庫だったので、どうしても「うぐいす荘」の印象が強い。でも原題は「Philomel Cottage」なので、ナイチンゲールの方が正しい。ナイチンゲールは小夜啼鳥(サヨナキドリ)とか夜啼鶯(ヨナキウグイス)という別名があるので、この「夜啼鶯」から「うぐいす荘」としたのだろう。日本にはいない鳥なので、鳴き声を想像させるためだったのかもしれない。でもナイチンゲールは夜鳴くし、鳴き声もうぐいすとは違う。作中でその鳥の声を聞く場面があるが(ロマンチックな状況で)、その時の鳴き声が二つの版では違うことになる。
タイトルとしては「うぐいす荘」の方が好きだけど、「ナイチンゲール荘」の方が原作通りなのだ。
今回どちらも読んでみたけど、当たり前だけど違いはそこだけだった。サスペンスの盛り上げ方はさすがで、思いがけないラストまで一気に読ませる。クリスティはやっぱり上手いなあ。
『白鳥の歌 クリスティ短編全集2』
アガサ・クリスティ/著 厚木淳/訳 創元推理文庫 1967年
『リスタデール卿の謎 クリスティー短編集11』
アガサ・クリスティー/著 田村隆一/訳 ハヤカワ・ミステリ文庫 1981年
昨日は寒かったのでちょっと厚着して読書会に出かけた。歩いたので少し暑くなり、帰宅後に薄手のカーディガンでいたら、夕方から更に気温が下がってうっかり風邪ひきそうになった。慌てて裏起毛のトレーナーを着た。パジャマも冬用、下着も長袖とズボン下で寒さ対策したので、暖かく寝られた。
しかし今朝は昨日よりもさらに寒く、ほとんど冬の格好をしている。急な気温の変化は勘弁してほしい。今夜はいよいよ毛布出した方がいいかな。
レポーターだった読書会が終わり、ほっと一息。しかし今度はメンバーの感想まとめがある。これがまた一苦労。今回レジュメ作成にかなり苦戦したので、少し休んでから取り掛かろう。
でもあんなに苦労したレジュメに記載間違いがあり、しゅんとしている。発表途中で気づいたので、参加メンバーには訂正をお願いした。何度も読み直したはずなのになあ。
散歩の途中で見つけたイシミカワ。葉っぱは三角、小さな丸い青やピンクの実がある。ちょっとこの写真ではわかりにくいけど、実がついてる葉は丸くて、ちょうど丸いお皿にのっているように見える。
ガザではまたイスラエルの攻撃が再開されているという。ハマスが停戦協定を破ったという理由らしいが、たぶんそうやってまた攻撃するだろうということは、うすうす予想はしていた。そしてまたイスラエル寄りの報道が続くのだろうと思うとやりきれない。
新宿での「NO HATE集会」もっと近ければ参加したかった。でもそれも言い訳にすぎない。本気ならちゃんと行動を起こせるはずなのに、ぬくぬくと家で嘆いているだけだ。情けない。
GPSフランス大会。いい演技と高得点が続出しているのに、アイスダンスのシャルマルの点数が伸びないのが悲しい。
寒くなると物悲しくなる。暑い時は熱中症が心配で、早く涼しくなれと思っていたのに。勝手なものだ。
今度はBlu-ray。
とにかく早く見たい!という欲望を優先して、すぐ手に入るDVDをまず注文。ほぼ毎日楽しんだ後、入荷待ちだったBlu-rayが届いた。
本編再生。やはり画質が良い。暗くても細かいところまで見える。満足。
そして目当てだった特典映像。各種予告編、メイキング、インタビュー、削除シーンなどなど。大満足。
削除シーンを見ると、あ、あのシーンの前にはこんなエピソードがあったのか、と納得できた。特に大ボス、王九をもっと労ってやってよ。あんなに頑張って尽くしてるのにさあ。かわいそうじゃないか。初見の時は、ただただ怖いヤバい強い、とんでもないヤツとしか思えなかった王九を、こんな目で見る日が来るなんて。
今週から始まったフィギュアスケートグランプリシリーズ。観戦してる人のSNSで写真や採点を見られるけど、ずっと追ってるわけにもいかないので、だいたい結果だけをISUのリザルトページで確認する。それでもついつい気になって夜中にSNSやリザルトページを見たりするので、寝不足になってしまう。この季節毎年悩ましい。